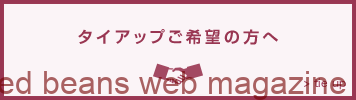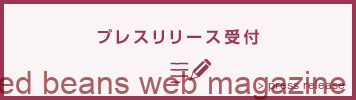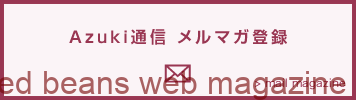小豆を世界にプロジェクト。リーダーの和田美香です。
あずき大好きです。
大福も大好きです。
なんだ結局、小豆を世界にといいながら、大福食べて、甘いあんこで小豆をたべてるじゃないか。
そう突っ込まれそうですね。
悩んでいたこと
あまりに、あんこも大好きなので、困ったなあとおもうことがあります。
一日に大福一個だけ、あんこスプーンひとすくいだけにしておくことができません。
砂糖が気になります。
体に良いものも、適量でなければ全然体に良くなくて、体に逆に負担をかけることも知っているのに、たくさん食べたくなるからです。
小豆は身体にいい。
でも、あんこは、砂糖とのつきあいも、ついてくる。
砂糖の量が気になって、なんとなく、わたしの中であんことして小豆を、食べることがモヤモヤしていました。
そしたら、腸内細菌と肥満や健康のことを説く本と出会って、小豆を甘いあんこで食べることつまりあんこの砂糖を許すきもちが生まれました。
この記事ではその本2冊をご紹介しながら、小豆の良さと砂糖をゆるすは、どこから生まれたかお伝えしたいと思います。
あずきに含まれる食物繊維がなぜ体に良いのか
食物繊維がたくさん豆類には含まれています。
また小豆の炭水化物は、難消化性デンプンです。
小豆の栄養成分をそんなふうにご紹介すると、女性の誰もが、体にいいよねと嬉しそうに反応してくださります。
でも、そう話すわたし自身、食物繊維がそもそもなぜ身体にいいのかしりませんでした。
食物繊維はただの腸のおそうじに必要だということぐらいの感覚でした。
それが、この本では、食物繊維がなぜ、腸に必要なのかが、説かれていました。
『あなたの体は9割が最近微生物の生態系が壊れ始めた』アランナ・コリン著,河出書房新社,2016年。
食物繊維は、私たちの小腸や大腸に住む、微生物たちに必要な餌で、その微生物と共生してわたしたちが健康を保つために、餌を与えてやる必要かあるからだそうなんです。
少し前までは肥満や肥満の原因は、カロリーのインプットとアウトプットのバランスが悪いから、と言うふうにされていました。
ところが最近の微生物学の研究の知見から見ると、太ったりするのは脂肪や炭水化物の摂取量が関係するのではなく、食物繊維の量と関わりがあるのだそうです。
食生活全般において脂肪や合成炭水化物を含む食品の摂取比率が高まれば、胃袋の量は一定なので、食物繊維を含む食品の摂取比率は、必然的に下がります。
したがって食生活の変化によって、食物繊維の量がへったから、肥満の増加を招いたと言うのです。(216頁)
食物繊維は、そのほとんどが野菜にも、穀物にも、豆類 といった炭水化物にふくまれています。
砂糖も炭水化物、ごはんも炭水化物、小豆の栄養成分も炭水化物、みな同じ炭水化物に分類されるのに、どうよくて、どう悪いのか。
米や豆類は難消化性デンプンでにあたります。
炭水化物の生成具合と、分子の大きさに着目するといいのだそうです。
ケーキは60%が炭水化物でできていて、それは精白小麦粉と砂糖が入ってて、分子がちいさな炭水化物のため、小腸で素早く吸収されます。
一方、ブロッコリーもおよそ70%が炭水化物です。
でもその半分は食物繊維で、大腸の微生物によって分解、消化されます。
炭水化物を含む食品の範囲は広い。純粋な精白小麦粉で作られた白パンから、難消化性の食物繊維を含む玄米までいろいろあります。
筆者は、「体炭水化物ダイエットで小さいいっぱいのジャムと芽キャベツいっこ同じように悪者扱いして避けてしまうと、食物繊維の摂取量が少なくなる」(222ページ)と言っています。
炭水化物を、食物繊維の含有量ではかって食べてみてはどうかと、提案してくれています。
また、砂糖も、生成されて100%小腸で吸収される精白糖と、ミネラルがたくさん含まれている甜菜糖やきび砂糖では、体への作用がちがうというのは、同じ砂糖といっても、組成が違うから吸収され具合がちがうのかと、素人ながらに考えました。
小豆のポリフェノールはなぜいいのか
食物繊維が豊富なうえに、小豆に含まれているポリフェノールはワインより3倍も多く含まれていると追いかけるようにご紹介すると、やっぱり和菓子食べなきゃと皆さん顔が輝きます。
あずきには、ワインよりも3倍多くポリフェノールが含まれています。
とはいえ、ポリフェノールも、抗酸化作用があるとしかしりませんでした。
身体が錆びることからまもってくれる、という程度の認識でした。
それをおしえてくたのが、この本でした。
『ダイエットの科学「これを食べれば健康になる」の嘘を暴く』ティム・スペクター、熊谷玲美訳、白洋舎、2017年。
ポリフェノールは腸内細菌を増やすことを積極的に助ける働きもしているのだそうです。(引用 111頁)
ポリフェノールは、細胞を傷つける化学物質が増えすぎればそれを取り除き、また炎症を沈める働きを持つ。(中略)腸内細菌にはそれ以上の役割があることが研究からわかっている。オリーブオイルに含まれる脂肪酸や栄養素の80%は完全に消化されないまま大腸に届いて、腸内細菌と出会う。そこで腸内細菌は、様々な種類の脂肪酸やポリフェノールを餌として食べ、それをもっと小さな不正生物に分解するのだがここで面白いことがいくつか起こっている。
その複製生物の1部は抗酸化物質として作用し、さらにポリフェノールを燃料費として使いながら様々な小さい中鎖脂肪酸を生成するのだ。中鎖脂肪酸は地味な名前の割にはなかなか興味深い化合物で、有害な脂肪のレベルを下げるよう体にシグナルを送ったり、免疫システムに次にすべきことを支持したりしている。一方でラクトバチルス菌などの細菌には脂肪の粒を掃除したり、固めたりして、血中から取り除く働きがあるが、ポリフェノールは、そうした細菌の繁殖を積極的に助けているまたポリフェノールは、不必要な細菌が町内で増えることを防いでいる。これによって下痢の原因になる大腸菌や胃潰瘍を引き起こすピロリ菌、さらに肺炎や虫歯の原因菌などへの感染が減るのだ。
適量に
腸内細菌の働きを促すに向いている小豆の栄養成分は、身体のなかにあったほうがいいものと感じます。
小豆を、餡にして食べると、砂糖がくっついてきますが、適量であれば、腸内細菌によい食べ物をとどけてあげたことになるのではと、思えた書籍でした。
砂糖は、小腸で吸収され、エネルギーになります。
でも、ちゃんと腸に食物繊維となる餌を、腸内細菌たちにとどけてあげたら、太りにくい働きをする菌たちも元気になります。
腸内細菌を養う食べ物として、適量の餡をたべる。
なあんだ適量かあ。
当たり前じゃないかとおもわれますか。
最後に、アランナ・コリンの書から、もうひとつ著者の言葉を紹介しておきます。
「あなたはあなたのたべたものでできている、とはよく聞くことばであるが、あなたはあなたの微生物がたべたものでできている、とも言える。食事のたびに、あなたの微生物のことをちょっと思いやってみてはどうだろう。あなたの微生物は今日、どんなものを欲しがっているだろう?」(228頁)
砂糖入りのあんこをたべることに、心の抵抗がなくなった本のご紹介でした。
和田美香

和菓子 薫風さんの とうもろこしのすり流しにおはぎがのった椀物。小豆にクコの実とハト麦にわあせ、熱や水分の排出をたすけることをねらった組み合わせと聞きました。
小豆のご購入はこちらから——————————–
■商品名 【北海道産小豆】晴れ晴れ小豆 600g
■単価 810円
■商品説明詳細
十勝の青空のもとで育った品種「きたろまん」です。皮の柔らかさが魅力。田舎じるこや小豆ご飯など、お気軽にお使いください。粒はやや小さめです。
■商品名 【北海道産小豆】晴れ晴れ小豆 5kg
■単価 4900円
【北海道産小豆】晴れ晴れ小豆 5Kg