
小豆が食生活のなかでポピュラーなのは、世界のなかでも、東アジアや東南アジア地域だけです。
東アジアや東南アジアのなかだけでみても、あずきに砂糖入れて甘くして食べるのがスタンダードと言うのは日本と台湾や中国の一部にすぎず、独自の文化といえます。
例えば、中国では、小豆は紅豆と呼ばれていて、甘くない紅豆粥にして身体をあたためるために寒い時期に食べられるのが一般的だとか。

どうして、日本で小豆に砂糖を入れ、餡にして小豆を食べる方法が一般的になったのか?
筆者は長らくずっと疑問に思ってきました。
小豆の第一人者として世界各国で研究成果を発表されている、あずき博士の加藤淳先生にもこの質問をぶつけてみました。
加藤淳先生からは、これはわたしの憶測に過ぎないけれどもねと、実験室での中で得られた体験から感じたことを教えてくださいました。
小豆の香り成分
加藤先生が小豆の研究を始められた時、ある日本人の方がこういったそうです。
「小豆って甘い香りがしますよね」
当たり前じゃないか、それは砂糖を入れたあんこの匂いじゃないのかと、口にしそうになって、ふと、そういえばと、小豆を煮た時の独特の香りを思い出したのだそうです。
そこで、砂糖入れない、小豆だけを煮たときの香りの成分を調べる実験を先生はされました。
オートクレーブという密閉された加熱殺菌の特殊な装置の中で、化学成分を抽出する実験です。
すると、確かに!
オートクレーブの蓋を開けると、とても甘い香りが。
この甘い香りの正体は、マルトールという成分でした。

他の豆や雑穀にはない成分で、小豆には多く含まれていました。
マルトールの甘い香りは、他の食べ物にたとえると、水飴のような甘い香りだそうです。
甘いもの同士をあわせる
小豆を煮たときに甘い香りがすることから、「もしかして砂糖入れたら合うのではないか」と、昔の人は発見し、試してみた。
そうしたら、とてもおいしかったのではないか。
小豆に砂糖を入れた入れた最初の人は、小豆に含まれる甘い香りの成分からくる、甘い香りをヒントにしたのではないか、というのが先生の仮説でした。
香の記憶が文化へと積み重なる
香りと出来事が結びつくと、とても強い記憶として脳に残るといわれます。
匂いが、海馬に直接情報をとどけるからだとか。
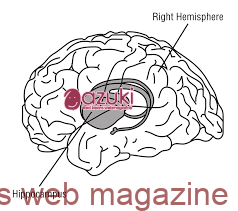
そう、たしかに、わたしもいま自宅のキッチンで小豆を炊いたら、その炊いている香りが鼻に届くだけで、すぐにもう40年以上前の昔の小さいころ過ごした奈良の風景と祖母の姿とが、ぶわっと目の裏に鮮明にカラーで蘇ります。
金にも匹敵する高価な砂糖を初めて煮小豆のなかに入れた人が感じた気持ちが、伝えられた人々も巻き込んでいったのは、甘い味ばかりでなく、香りの記憶としても魅了していったのかもしれませんね。
香りと記憶とが重なり、文化となったから、いま日本にいる人ならだれしもが、何かしら記憶に残る小豆にまつわるエピソードの数々を持つまでになっていったのではと感じました。
砂糖と小豆の出会いは、小豆の甘い香りからはじまったのではというあずき博士 加藤先生の仮説は、さらに、香りと文化の関係にまで、想いを馳せさせてくれました。
2018/2/2取材
<取材協力>
加藤 淳 様

地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 道南農業試験場 場長。農学博士。
北海道帯広生れ。帯広畜産大学大学院修士課程修了。北海道立中央農業試験場、北海道立十勝農業試験場、オーストラリア・クイーンズランド大学で豆類の品質・加工適性などを研究。
「あずき博士」として、講演活動や小豆をはじめとした豆の普及に幅広く取り組んでいるほか、世界でも小豆の第一人者として国際雑穀会議などにて研究発表活動も精力的に行う。主な著書に、『「あずき」のチカラはこんなにすごい!』(ロングセラーズ)、『小豆の力』(キクロス出版)など。監修に『あずき水ダイエット』(宝島社)など。









